社畜(しゃちく)とは、会社に飼いならされた家畜のように、自分の意思や自由を放棄して、会社のために働く人を揶揄する言葉です。
このことから多くの方は「会社に奉仕する人」をイメージされますが、単にそれだけではありません。たとえば一流のビジネスマンは自分の夢や会社の描く未来を叶えるため自分の時間を犠牲にし成果を出そうと努力していますが、彼らと社畜は明らかに違います。
社畜の本当の定義は「会社に従わざるを得ない人」です。
どういう人が社畜になるか?
ではどういう人が社畜になるのでしょうか?
特徴としては
・ストレスに弱い
・意思表示が苦手
・真面目すぎる
などの点があります。
心が弱く意思表示が苦手だと、周りの圧力に耐えられず言うことを聞いてしまいます。ストレスに強く不真面目であれば、「やっているフリで給料だけ貰う」などでそういった社畜環境に適応することもできますが、真面目だとそうもいきません。結果、言われるがままに働き、心をすり減らしていきます。
根本的な原因
とはいえストレスに弱くても、社畜にならず快適に働ける環境もあります。
結局のところ根本的な原因は「会社の環境」にあります。
具体的には
・労働者に成果を求めすぎる
・仕事にやりがいがない
の2つが重なると社畜が発生します。
労働者の仕事は「会社に奉仕すること」ではありません。「報酬ぶん働くこと」が労働者の仕事です。仮に報酬以上の働きを期待するなら、そもそもの認識が間違っています。
もちろん、世の中には自発的に報酬以上の働きをする労働者もいますが、それは仕事に「やりがい」を持たせることに成功しているからです。夢を感じられる仕事だったり、働くメンバーの雰囲気が良かったり、やりたいことを思う存分やらせてもらえたり。そういった「やりがい」を感じさせることができていない時点で「会社を成長させたい」と思う資格はありません。
そういう会社に未来はないので、早めに離れるのが理想です。
社畜の危険性
社畜環境が常態化しているとさらに危険な問題が起きます。
ここからは社畜環境が引き起こす「奴隷スパイラル」ついて解説します。
社畜の問題その1 部下にも社畜の働きを求める
社畜が部下の間はまだ平和です。むしろ会社からすればよく働く奴隷が手に入ってハッピーでしょう。
しかし社畜が上司という立場になったとき、状況は一変します。
部下にも社畜になることを強要し、環境がギスギスと悪化していく可能性が高いです。能力以上の仕事を押し付け残業を増やし、自分がやらされたからと同等の働きを期待し、部下は疲弊していきます。
こうして早期に退職されるか、部下自ら社畜となって環境に適応していきます。まるでゾンビのように増える社畜はなんとも恐ろしいものです。
社畜の問題その2 部下が育たない
仮に部下を社畜扱いせずとも、部下が育たない可能性があります。
社畜の中には自分で全て仕事を片付けようとしてしまい、部下に仕事を任せないタイプもいます。結果部下は暇になり、上司だけがいつもオーバーワークで勝手に自滅しているパターンはよく見られます。部下からしても仕事を与えられないのは逆にストレスになります。
しまいには自分で仕事を振らないくせに「部下が仕事をしてくれない」などとほざく始末。一度は目にしたことがある光景でしょう。
社畜の問題その3 環境改善ができなくなる
仮に会社の上層部に問題意識が芽生えても、社畜は環境改善を邪魔してきます。
業務効率を改善させると必ず発生するのが「暇になること」です。今まで時間のかかっていた業務を簡略化したり無駄な業務を省くことが業務改善なので暇になるのは当たり前なのですが、奴隷のように働くことで会社に貢献してきた社畜上司にとってこの「暇」は「自分の平穏を脅かす恐ろしいもの」という認識になります。
そのため、「簡略化したらミスが増えるかもしれない」「新システムをいれるとかえって混乱する」などと何らかの形で抵抗を見せます。業務改善を現場の上司に丸投げすると必ず失敗するので、注意が必要です。
社畜環境にいると気づいたら
もし自分が社畜環境にいると感じたら、できるだけ早く退職することをオススメします。転職でも良いですが、転職先を探す間にもストレスは溜まるので、辛いなら思い切って退職したほうが良いでしょう。
退職すれば心にも余裕ができ、スキルを磨く時間はできるし転職活動も上手く行くかもしれません。退職しづらいなら退職代行サービスを使うのも手です。
社畜環境にいると本来の自分を保てなくなるので、どんな手を使ってでも早めに離れることが大切です。一度離れてしまえば、本来の自分を取り戻し悠々自適に転職活動ができることでしょう。
ありがとうございました。

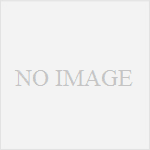
コメント