職場でよく耳にする上司の言葉「自分で考えろ」。
確かに、社会人として自分の頭で考える力を養うことは重要です。しかし、会社の仕事には考えて行動しても良いことと考えて行動してはいけないことがあります。その違いもわからず、全てを部下任せにする上司ははっきり言って無能です。
この記事ではそんな無能上司の問題点についてまとめます。
仕事を教えないと何が起きるか
上司が「自分で考えろ」と言って具体的に教えない場合、まず起きるのは部下の混乱と時間の浪費です。
基礎的な知識やルールがわからない状態では、いくら自分なりに考えても的外れな行動になりがちです。たとえば、営業資料の作成方法や顧客対応のルールなど、会社によって異なる部分を学ばずに独自判断で進めると、修正ややり直しが発生します。
結果として、本人は「努力しているのに評価されない」と感じ、モチベーションを失います。さらに、間違ったやり方が組織内に広まるリスクも生まれます。
勝手にやられると困る仕事は教えるべき
会社の業務の中には「自分の判断で工夫して良い部分」と「決して勝手にやってはいけない部分」が存在します。
例えば、法的な書類の取り扱いや契約条件の調整、経理処理の方法などは、誤れば重大な損害やトラブルにつながります。こうした仕事を部下が独断で進めることは極めて危険です。上司が「考えてみろ」と丸投げするのは責任の放棄であり、リスク管理ができていない証拠です。
そのような前提を無視して、個人的な判断で勝手に部下任せにするのは無能以外の何者でもありません。最初にしっかりルールを教え、その上で裁量を与える範囲を明確にすべきです。
自分で考えさせると属人化が進む
「自分で考えろ」としか言わない環境では、部下は自分なりの方法で仕事を進めるようになります。すると、同じ業務であっても人によって手順や基準が異なり、結果的に属人化が進みます。
属人化した業務は、担当者がいなくなると引き継ぎが困難になり、組織全体のリスクになります。会社として本来必要なのは「誰がやっても一定の品質で進む仕組み」です。部下に自由にやらせて終わりではなく、知識やノウハウを共有し、標準化していくのが上司の役割です。
そういった職務を放棄することは、上司自ら会社を腐敗させているに等しく罪深いことです。
業務効率の低下に繋がる
教えない上司の下では、部下は常に「これで合っているのか」と不安を抱えながら試行錯誤することになります。
確認や修正が増え、最終的に業務全体の効率は著しく低下します。さらに、指導不足によって発生したミスの修正には、上司や他のメンバーの工数も割かれます。結果として、チーム全体の成果は伸びず、残業や負担の増加を招きます。「教える手間を省いたつもりが、後で倍の手間を生んでいる」状態こそが、教えない上司の典型的な問題です。
最悪なのは上司自身それに気づかず、「部下の確認が甘い」「ちゃんと仕事をしろ」などと言い始めることです。こうなるともう救いようがありません。
教えない上司は自分の仕事を理解できていない
そもそも部下に教えられない上司は、自分が日々やっている仕事を正しく言語化できていないケースが多いです。経験や勘に頼って業務をこなしてきたため、「なぜこの手順が必要なのか」「どう判断すべきか」を説明できないのです。
これはプレイヤーとしては優秀でも、マネジメントとしては未熟であることを意味します。上司の役割は成果を出すだけでなく、再現性のある方法を部下に伝え、チーム全体の力を底上げすることです。
自分の仕事を体系化できない上司は、部下にとって無能に映って当然です。
上司の質を評価できない会社の責任でもある
問題の本質はこういった「上司のマネジメント不足」を正しく評価できない日本の人事制度にあります。経営者からすると「沢山働いて成果を出してくれる人を上司に」となるのですが、それが過ちです。
上司の適性は「成果を出す人」ではなく「人を育てる能力のある人」「無駄を減らし社内環境を正常化できる人」にあります。成果だけを見るとそういった能力が評価できず、適正のない人間を昇進させてしまい、結果会社の業績低下を招きます。
また、上司になった人間の評価システムが存在しないことも問題です。部下からの信頼や、どれだけ部下の能力が伸びたかを評価せず、「部署全体の業績」で評価してしまうので、それが上司の責任なのか部署全体の能力不足なのかの判別ができません。
当然上司からすれば自分のせいとは認めたくないでしょうから、業績のために部下を叱責するパワハラ環境ができあがります。
全ての根本原因は、「上司の質」を評価できない、日本の人事評価制度にあるのかもしれません。
もしそのような環境に辟易したら、転職の準備を進めることをオススメします。世の中には良い会社もありますので。
ありがとうございました。
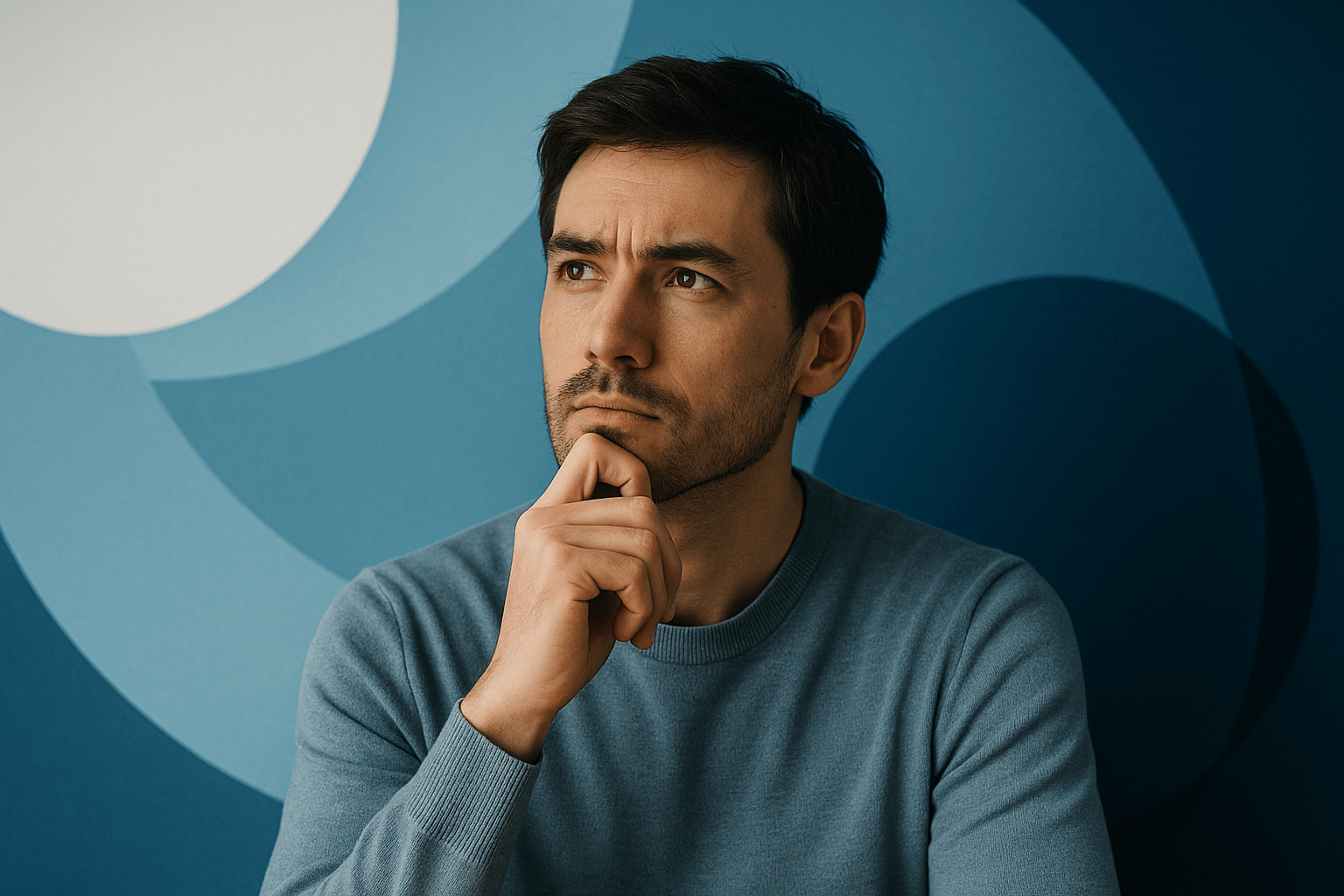
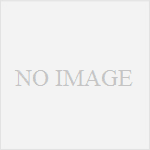

コメント