最低限の仕事すなわち「言われたことを言われた通り、期限に間に合うように仕上げた」にも関わらず、文句や小言を言われ、上司からの扱いが悪くなった経験はありますか?
あるいは納期に間に合うように仕事しているにも関わらず「もっと自発的に貢献してほしい」と言われたことはありますか?
実はこれ、労働契約的に非常に「不適切」な扱いである可能性が高いです。
問題の整理
今回の問題点は2つ
- 労働者として最低限の仕事はしていること
- にも関わらずそれが「努力不足」のように扱われること
一般的な見解
Q.労働者が最低限の仕事をこなしているにも関わらず、それを「努力不足」として報酬以上の働きを期待することは会社として適切ですか?
A.会社が労働者に対して「最低限の仕事」をこなしている状態を「努力不足」と評価し、報酬以上の働きを当然のように期待することは、適切とは言えません。
1. 労働契約・就業規則との関係
労働契約や就業規則には、労働者が担うべき業務内容やその範囲が定められています。労働者がその内容に沿って最低限の義務を果たしているのであれば、契約上の責任は十分に果たしていると考えられます。
2. 「努力不足」の基準の曖昧さ
「努力不足」という評価は主観的であり、客観的な業務基準に基づいていない場合、評価の公平性・納得性を欠きます。
労働者が最低限の業務を正確に遂行している場合、それ以上の「努力」や「成果」を一方的に求めることは合理性に欠けます。
3. 報酬と期待値のバランス
報酬(賃金)は、通常その職務に対する労働の「期待値」に見合った水準で設定されています。
最低限の業務遂行=報酬に見合った働き、であり、それ以上を求める場合は追加のインセンティブや職責・報酬の見直しが必要です。
4. モチベーション・組織運営への悪影響
報酬以上の働きを強いる風土があると、労働者のモチベーション低下、職場への不信感、離職率の上昇など、組織全体に悪影響が生じやすくなります。
5. 社会通念・倫理的観点
社会通念上も、「契約や規則に沿って働く」ことが評価の基準とされるべきであり、過度な努力や無償の奉仕を当然とする企業姿勢は倫理的にも批判されやすいです。
まとめ
- 労働者が最低限の業務を適切に遂行している場合、それを「努力不足」と評価し、報酬以上の働きを当然のように期待することは会社として適切とは言えません。
- 追加の努力や成果を求める場合は、それに見合う評価・報酬制度を設けることが不可欠です。
現実的にも、そうした姿勢は組織運営上のリスクとなるため、慎重な対応が求められます。
そんな都合の良い社員はいない
以上、一般的な見解でした。
意識の高い人間がよく「経営者目線を持て」などと語っていますが、それは自発的に成長したいと思ったときに自分で実行することであり、部下や他人に強要すべきことではありません。
もし部下に経営者目線を持って行動させたいなら、「経営コンサルタント」として報酬を引き上げるのが本来なやり方です。それができないのであれば、労働者として報酬ぶん働いてもらうだけです。
まぁでも、気持ちはわかります。そりゃあ上司からすれば報酬以上に働いてくれる部下ほどウハウハな人材はありません。そういう部下を期待してしまうのは仕方のないことです。
とはいえ、考えが浅はかすぎます。そんな白馬の王子様みたいな人間そう簡単に現れません。仮に現れても白馬の王子様はお前みたいな不機嫌ヅラの無能中年上司には微笑みません。優秀な人間は優秀な人間と惹かれ合うのが世の常。いつまでも寝言言ってないで黙って自分の仕事やってろ。
転職か静かな退職をしよう
ということで「報酬以上に働く必要がない」という話でした。
そんなことを要求してくるブラック企業に勤めてしまったら、スキルだけ盗んで転職するか「静かな退職」を選択しましょう。ただしクソ上司がいるならできるだけ早く退職することをオススメします。ストレスは脳を破壊しますから。
ありがとうございました。

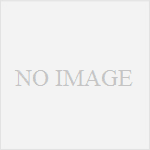
コメント